2022年1月17日にゆうちょ銀行で今まで無料だった硬貨の取り扱いにおいて枚数によって手数料がかかるようになりました。
こうした手数料は大手銀行がすでにおこなっていたのですが、「最後の砦」だったゆうちょ銀行の有料化は様々な所で影響が出る可能性があります。今回は硬貨取扱有料化について書いていこうと思います。
1.そもそもなぜ有料化になったのか?
低金利政策、人口の減少などで今まで無料だったサービスを維持することが困難となっており、経営環境悪化を懸念した金融機関が2019年ごろから相次いで大量の硬貨を取り扱う際に手数料を徴収するようになりました。
2.なぜ硬貨だとお金がかかるようになったのか?
硬貨の取扱は紙幣に比べるとコストがかかるからです。
持ち込まれた硬貨は専用の機械で種類や枚数を計算しますが、その際、変形した硬貨や外国の硬貨、もしくはメダルゲームのコインなどが混じっていることがあり、機械が故障することがありました。その修理費や、重くて輸送に手間がかかるので輸送費や、保管費に相応の金額がかかることになり、金融機関によってはコストが年間数億円にも登る場合もあるそうです。
3.では、手数料はいくらになる?
ゆうちょ銀行の場合は窓口とATMでは手数料の金額が違います。
窓口の場合
1〜50枚……無料
51〜100枚……550円
101〜500枚……825円
501〜1,000枚……1,100円
(1,000枚以上は500枚毎に550円加算)
ATMの場合
1〜25枚……110円
26〜50枚……220円
51〜100枚……330円
(ATMの場合は100枚までが預金の限度となっています)
上記はゆうちょ銀行の場合です。他の金融機関を利用する際はその機関で定めらた手数料を予め調べることをお勧めします。
4.硬貨の取扱有料化でどんな影響があるか?

今回の有料化によって多大な影響を受けているのが普段から硬貨を扱っている神社などは、お賽銭の大半が硬貨なのでその対応には苦慮していて、一部の寺社では電子マネーでお賽銭を受け付けるという動きもあるそうです。
また、募金箱などを設置している慈善団体も頭を悩ましているそうで、募金のほとんどが1円や10円などの硬貨の積み重ねが活動資金となっているので、今回の件で集めた募金が目減りしてしまうと同時に募金した人たちの善意が手数料で消えてしまうことに心を痛めているそうです。
5.今後の展望として?

今回のゆうちょ銀行の手数料導入の流れは経費削減がその原因となっています。金融機関本来の業務であるお金の管理、保管、もしくは運用などの業務だけでは経営が成り立っていかなくなっている現在では、さらなる手数料の値上げが考えられます。この流れによってさらにキャッシュレス化が進み、現金でのやり取りが少なくなってくる可能性がでてくるのではないでしょうか。これからは貯金箱に小銭を貯めていた風景も日常から少なくなっていくのかもしれません。
6.こんな動きも出ている
このような動きの中、大阪にある神社では地元の商店街とタッグを組んで、コインと紙幣を独自に両替するという取り組みを始めています。
具体的には神社に集まった硬貨を金額ごとに50枚づつ束にして、小銭が必要な商店がそれを紙幣と交換するというものです。現在、紙幣を硬貨に両替するにも手数料が発生するというなか、お互いがお互いを補う形で取り組む動きは手数料対策の一案として注目されています。
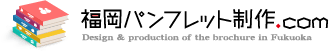
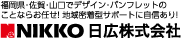
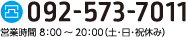
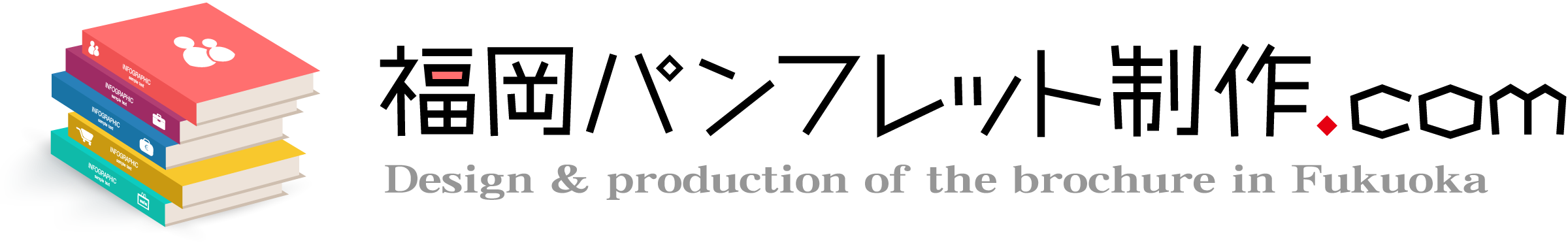




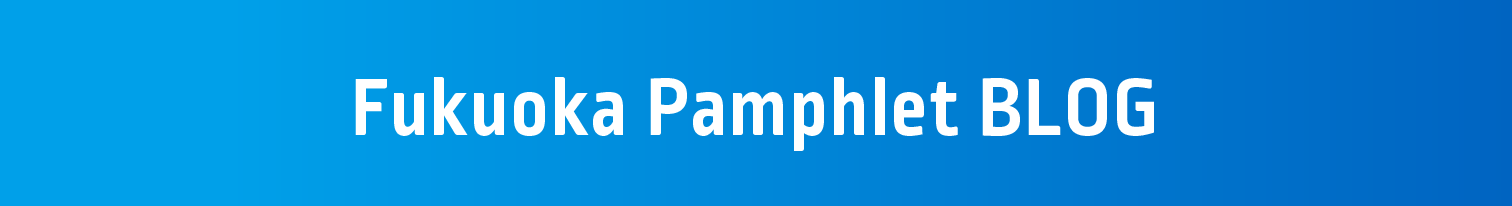




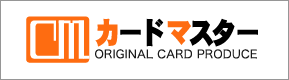

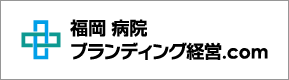
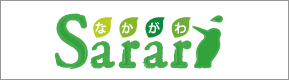
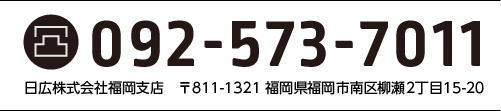


 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら